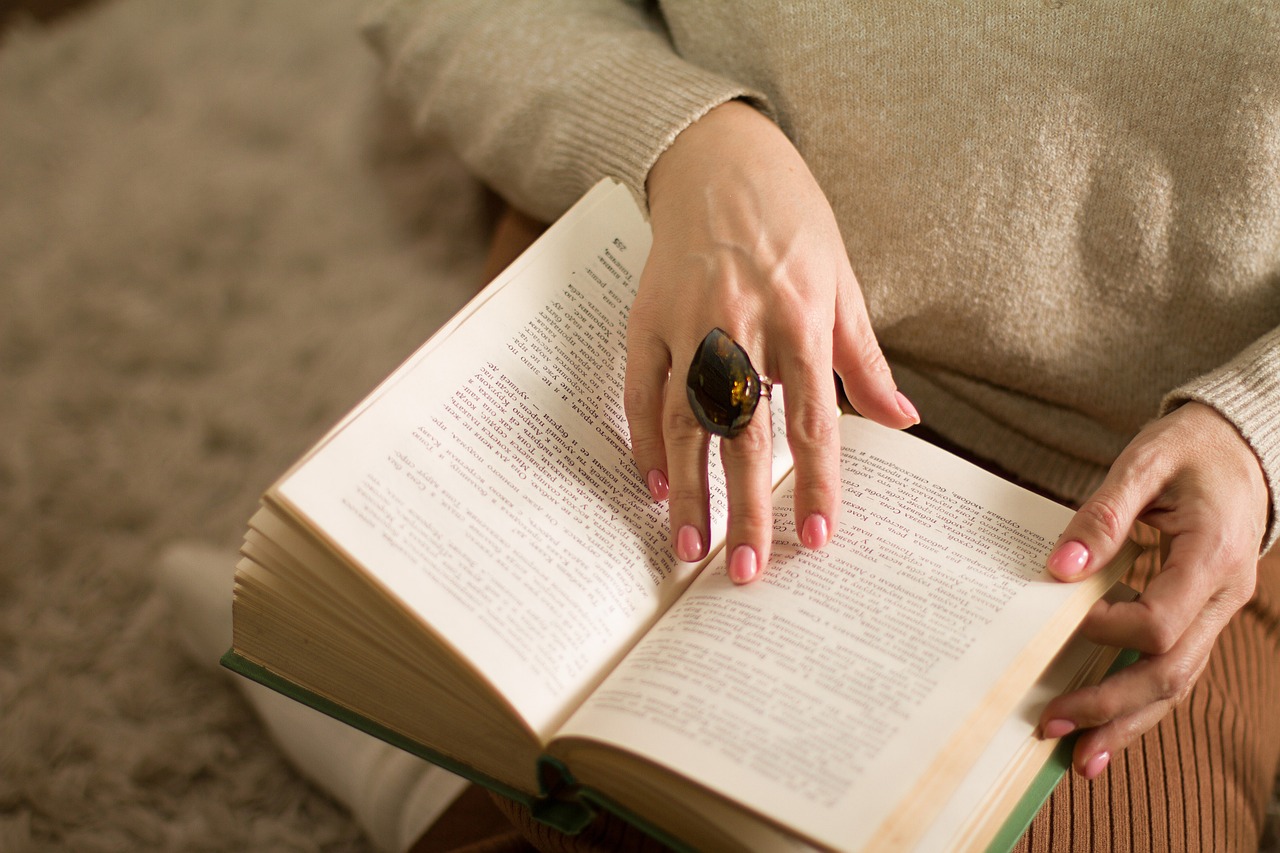日本のビジネス史と起業家精神、そしてイノベーションに興味がある読者にとって、菊川武夫氏による『History of Innovative Entrepreneurs in Japan』(Springer、2023年刊)は見逃せない一冊だ。本書は、日本の経済発展と企業家たちの軌跡を17世紀から現代まで辿る壮大な歴史的探求であり、個人の伝記と国全体の産業成長の融合を描いている。
著者の菊川氏は、新潟県にある国際大学で経営史を教える教授であり、東京大学および一橋大学の名誉教授でもある。本書では、20人を超える日本の起業家の人生と業績に焦点を当て、近世から現代に至るまでのイノベーションと経済発展の背景を紐解いている。
本書の特徴は、そのボリュームと一貫性にある。291ページにわたる本書は、20のケーススタディで構成されているが、その大半は菊川氏本人が執筆しており、長年にわたる研究成果の結晶とも言える内容だ。複数の著者による論文集ではなく、統一された視点から描かれている点も評価に値する。
停滞経済の原因を歴史から探る
菊川氏は、単なる過去の記録にとどまらず、日本経済がバブル崩壊後に長く続く停滞に陥った原因を探ることも目的としている。彼は序文において「日本経済の真の減速要因を解明することは、経営史家として日本経済再生の可能性を模索する上で不可欠な課題である」と述べている。
過去を学び、未来に生かす――本書はその姿勢を貫いている。
日本経済の転換点を探る3つの問い
本書では、以下の3つの問いを軸に分析が展開されている。
-
日本はなぜ非西洋諸国の中で最も早く産業化を成し遂げたのか?
-
なぜ1910年代から1980年代にかけて、これほどまでに経済成長を遂げられたのか?
-
なぜ1990年代以降、経済が停滞しているのか?
初期の産業化は、伝統的な手工業活動と西洋技術の導入によって実現されたとされており、高度経済成長期には体系的なイノベーションと効率的な経営手法が寄与した。一方、停滞期は、世界的な破壊的イノベーションへの適応の遅れに起因すると指摘されている。
歴史を3つの時代に分けた構成
本書は、以下の3つの時代に分かれて構成されている。
第1部:ブレイクスルー・イノベーションの時代
江戸時代から明治時代を対象とし、「港の開国から日露戦争後まで」と題した章では、日本の初期産業化の試みとそれを支えた起業家たちを紹介。河内屋善右衛門、三井高利、中井源左衛門、中川彦次郎、岩崎弥太郎・弥之助兄弟、安田善次郎、浅野総一郎、渋沢栄一といった名が挙げられている。
各時代の冒頭には概観があり、末尾には比較・考察のコーナーが設けられている。特に「日本は産業化における遅れた国だった」という視点からの分析(p.85)が印象的だ。
第2部:漸進的イノベーションの時代
第1次世界大戦から1980年代までの時期を扱い、技術の進化とそれが長期的成長に及ぼした影響に注目している。ここでは、小林一三、松永安左エ門、鈴木三郎助(二代目)、豊田喜一郎、野口遵・鮎川義介、出光佐三、西山弥太郎、松下幸之助、井深大、盛田昭夫、本田宗一郎、藤沢武夫、土光敏夫といった近代企業を牽引した人物たちが登場する。
彼らは日本の経済成長、高度な技術革新、そして世界市場への躍進に大きく貢献した。
第3部:「2つのイノベーションの狭間」にある時代
1990年代以降の現代に焦点を当てた章では、日本型経営の機能不全が語られる(p.222)。ここでは、稲盛和夫(故人)、鈴木敏文、柳井正、孫正義といった現代を代表する企業家が取り上げられている。
未来を見据えた歴史書
菊川氏の書は、単なる過去の列挙ではない。現在の課題を照らすために、歴史を素材として用いた一種の「未来志向型の歴史書」でもある。読み進めるうちに、現代のビジネス環境や経済の停滞についても多くのヒントが得られるだろう。